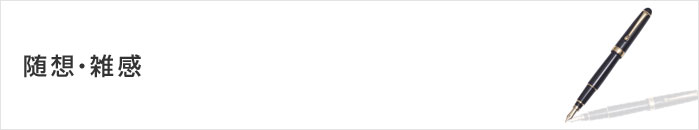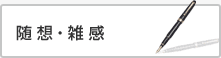退任にあたり、今を見つめて
前評議員 津志田 藤二郎
2011年(平成23年)不二たん白質研究振興財団の評議員に就任し、今年5月満期で退任しました。1979年に設立された前身の「大豆たん白質栄養研究会」から、今年で45周年を迎えるこの財団が定款に「たん白質に関する研究及びこれに関連する研究の奨励、援助」を掲げ、大豆を始めとする植物タンパク質研究に果たした貢献は計り知れず、評議員として財団活動に参加させて頂いたことを大変有難く思っております。関係者の皆様に心よりお礼申し上げます。
御存知のとおり、国連のデータによると2050年までの世界の人口は今後18億人程度増加し約100億人に達し、平均寿命も約6歳ほど延びる見通しのようです。
100億人の食を賄うための食料生産が今後の大きな課題ですが、栄養素の中では特にタンパク質の供給がひっ迫する可能性が高く、Proteincrisis(プロテンクライシス)に向けた大豆たんぱく質を始めとする植物たんぱく質などの有効利用技術の開発と、高齢化に向けた健康増進作用の解明と産業化などが世界的視点から求められているようです。
当財団の助成による研究は、大豆などの遺伝・育種・成分・品質から調理・風味・加工・物性、さらには栄養・健康・疾病予防・治療など幅広く実施され、研究成果は飛躍的に増加していますので、それらが今後プロテインクライシスへの対応技術開発や食による健康増進などの産業技術へとつながるものと固く信じています。
ところで、いち早く超高齢社会に突入した日本は、世界に先駆けて保健機能食品制度を導入しましたが、機能性表示食品の一つである「紅麹サプリメント」による大規模な健康被害(尿細管壊死)が2024年3月に発表されました。
紅麹を培養する際に混入したアオカビが毒成分を生産したことによる事故なので、今後は機能性表示食品GMPあるいは保健機能食品GMPの基準や健康被害届け出義務などが整備されることになるものと思われますが、保健機能食品に関する信頼の回復には時間がかかりそうで大変です。話題になったアオカビ毒素について調べて見たところ、微生物間の相互作用に興味を惹かれました。
紅麹サプリメントに混入した3成分の異物の内、化学構造が明確でしかも尿細管壊死作用が確認されたものはトロポロン類(トロポノイド)に属するプベルル酸のようですが、実証研究はまだ継続されています。
トロポノイドの中で日本で最も有名なものはヒノキチオールで、コルヒチンやテアフラビンもその仲間ですが、実は基本骨格のトロポロンそのものが、湖沼などの環境中に存在している可能性があり、中国では地域ごとのトロポロン分布が既に調査報告されています(Environ.Sci.Technol.52(9),5105-5114(2018)。
トロポロンは「イネ苗立ち枯れ細菌病」の関与毒素として日本で1985年に発見されました。田植機の開発により専用の苗箱での苗生産が行われるようになり、これまでの苗代(なわしろ)と常在微生物群が変わったことで顕在化したようです。
その後、苗立ち枯れに関与する病原菌(Burkholderiaplantarii)に、 トロポロン生産を抑制する拮抗細菌(Burkholderia cepacia)と助長するヘ ルパー細菌(Sphingobium yanoikuyae)が影響を与え、トロポロン生産量 が制御されていることが明らかになり、それら細菌の関与物質も解明され ていました。
トロポロン生産菌は、イネの他に畦畔雑草や河川敷・湖沼や湿地帯にあるススキ、アシなどにも感染するとのことなので、日本全国に分布していると推察されているようです。従来の苗代でイネ苗を育てていた頃には、トロポロン産生病原菌の他に、拮抗細菌やヘルパー細菌などが混在し、宿主であるイネ苗などを枯らさないように共存していたのでしょう。
多くの細菌は増殖しすぎて宿主を死滅させないためのクライオセンシング機構(定足数管理)を持っていて、多数の細菌が共存するバイオフィルム内では、クロストークにより複数の共存菌類の菌数が一定に保たれているそうです。
当財団では腸内細菌に関する研究課題も多数実施されていますが、腸管内のバイオフィルムや細菌間のクロストークなどに興味を感じます。
「ヒト常在細菌叢と健康・疾患に関する研究」もかなり行われているようで、紅麹菌サプリメント問題から、意図せず、生活圏環境に共存する常在細菌群の巧妙な相互作用に対する理解と、多様性の大切さを知らされた思いがしています。
〈宮城大学名誉教授〉