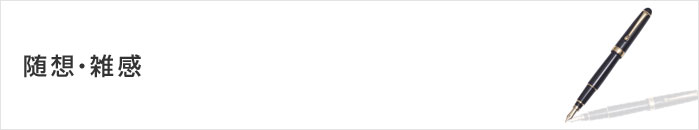大豆たん白質の固有熱伝導度
選考委員 矢野 俊正
私は元々は微生物屋だった。それが、どういう運命の悪戯か、東京大学農芸化学科に新設された食品工学講座を担当することになった。食品にも工学にも素人の者が選ばれたのが異常なら、助教授の身分での講座担当も、発令が年度末の3月1日付(1971年)なのも異常だった。後で調べた所によると、文部省が同講座の設置を認めたのは1968年のようだから、当時の選考委員の先生方が人選にかなり苦慮された形跡が窺える。
覚悟はしていたものの、突然専門を変えるのは容易なことではなかった。何をすればよいのやら皆目見当がつかない。身近には、工学と聞くと虫酸が走る、という大先生が居られたし、工学という名がついた食品製造の本は売れない、と言われた時代だった。海外では既に "Food Engineering" と題した本が出版されていたが、その主たる内容は、化学工学の単位操作論の紹介だった。しかし、それなら、何故化学工学の必要性が強調されずに食品工学なのか?情報収集を始めて間もなく、私は奇異なことに気付いた。
戦後日本の経済高度成長が始まったのは昭和30年(1955年)頃からである。食品加工も大規模化し、機械化・装置化も進んだ。工学系の人々も「食品産業」で働くようになった。しかし、機械・装置内で起こる変化の予測と制御に関しては、昔と同様、勘と経験が支配していた。助けを求められたと見られる工学系の先生方も、進んで食品加工に近づこうとはされなかった。なにやら魔物がいる、これが私の直感だった。
魔物の正体を見破るまでにはいろいろ戦略を練る必要があったのだが、日成らずしてその正体が分かった。原料は生物素材、最終製品は消費者の嗜好に合っていなければならない、という食品加工の入口と出口の制約が問題の発生源である。生物素材は、微分方程式の具体解を求める段階で必要な物性値が不定という大問題を工学者に突きつける。嗜好に対応するためには各種単位操作が多目的に成らざるを得ないが、どれだけの因子をどんな範囲に制御すべきかという目標が明確ではない。つまり、現在の科学・工学の論理体系を安易には導入できないのである。では、どうすればよいのか?この問いに答えられる人は誰もいなかった。振り返ると、21年に及ぶ私の食品工学研究のかなりの部分は、生物素材の不定な物性値をどう体系的に把握するかに注がれた。暗中に模索の中、最初の光明を見出したのが大豆たん白質の固有熱伝導度値の推定だった。
伝熱操作は食品加工で最も日常的な操作だが、生物素材の熱伝導度(不均質な材料では"有効"の字を冠して呼ぶ)は便覧に載ってはいない。測定されなかったのではなく、300を超す原著論文の様々な生物素材での測定値を知っても、与えられた材料の有効熱伝導度はまったく予測できなかったのだ。ある段階で、値は材料の成分組成と "構造"(各種成分の空間配置状態)で決まる、と睨んでいたのだが、構造の取り扱い方が解らない。ある日、成分組成は変数だが、構造は変数を結びつける関数形で表現される、と閃いた時、研究の展望が拓けた。成分ごとに固有の熱伝導度(固有熱伝導度)と多様な構造に対応する関数形とが整理されれば、不定な物性値の体系的把握が可能になる。
しかし、ここにも2種の難関が待ち受けていた。食品の4主成分を糖質、たん白質、脂質、水としたとき、脂質と水の固有熱伝導度値は測定可能で既知の測定値が利用できたのだが、糖質とたん白質の固有熱伝導度値が分からない。精製したときに粉末になってしまう成分に対しては、固有熱伝導度値の直接測定法はないのである。関数形の整理も難関だった。それまで理論式や経験式合わせて20余種の関数形が文献上で提案されていたが、理論式の前提はそのままでは生物素材に当てはまらないので、どんな場合にどれを使えばよいのかが分からない。固有熱伝導度と関数形とは、どちらかが分かれば他も分かる関係にあるのだが、生物素材に対しては両者とも不明だったので、全てが混沌としていたのである。
ここから先の説明は省略しよう。まだまだ苦労の種は尽きなかったのだが、幸運もあって、私たちは初めて大豆たん白質(脱脂大豆から熱水抽出され、CaCl2で凝固した区分)の固有熱伝導度値推定に成功した。これが突破口となって、いろいろなたん白質や糖質の固有熱伝導度値が推定され、同時に、どのような場合にどんな関数形を使えばよいかも整理され、不定だった食品素材の有効熱伝導度値は、一応体系的把握が可能になった。人々に注目される研究ではないが、私にとって、大豆たん白質の固有熱伝導度値推定は思い出深い研究である。農芸化学出身という経歴がこのような研究を着想させた、とも思っている。
〈東京大学名誉教授〉